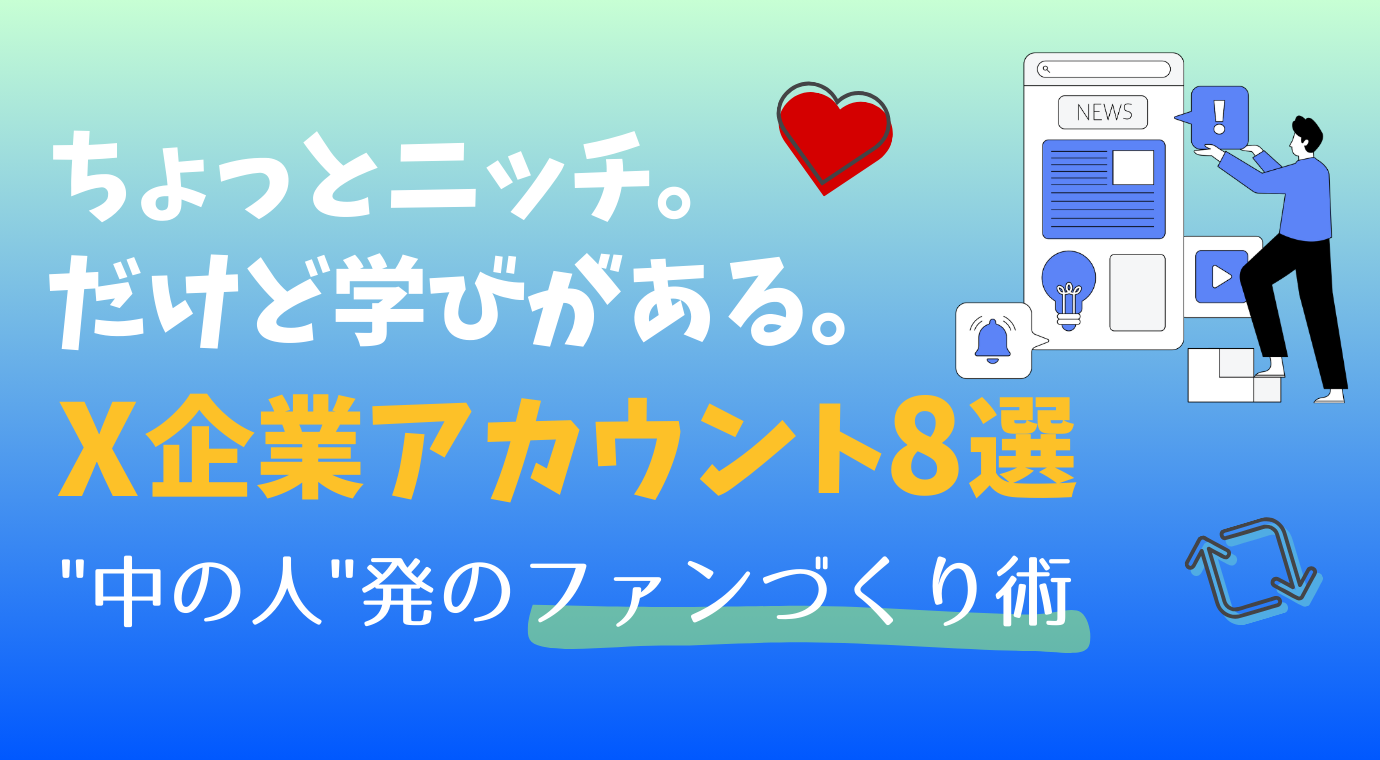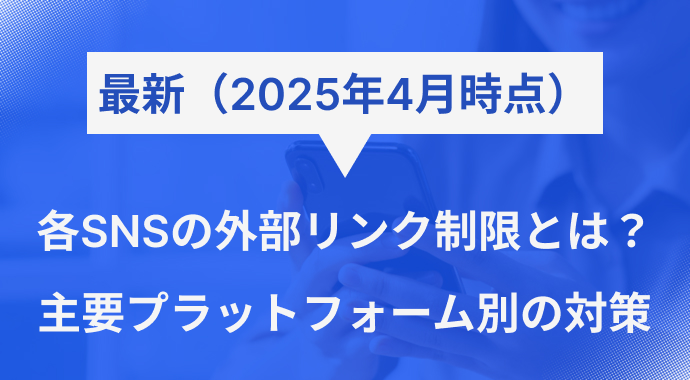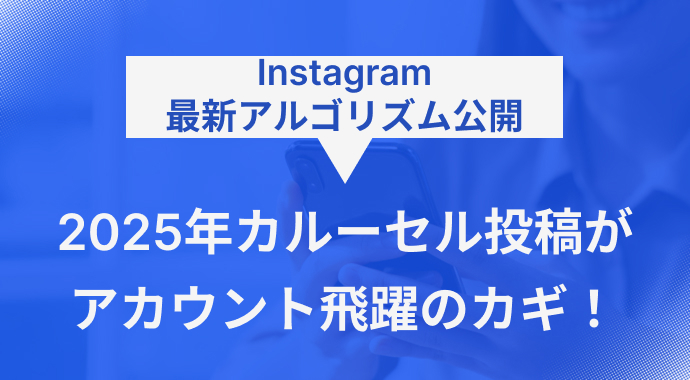SNS、とくにX(旧Twitter)は、企業にとっても重要な発信チャネルとなりました。新商品のお知らせやキャンペーン情報を投稿するだけでなく、企業の姿勢やカルチャーまでもが“中の人”の言葉を通じてユーザーに伝わっていきます。
でも、実際に運用するとなると悩みもつきもの。
「何を投稿すればいいのかわからない」「誰にも見られず虚無…」「企業っぽすぎても人っぽすぎても不安」──そんな声を、日々X運用を担当する皆さんからよく聞きます。
そんな中、いきなり有名な大企業のアカウントを参考にしようとすると、「うちとは規模が違いすぎる…」と感じてしまうことも。実は、もっとヒントになるのは“有名すぎないけれど運用がうまい”企業アカウントたちです。
そこで今回ご紹介するのは、「ちょっとニッチだけどすごく参考になる」企業Xアカウント8選。
どのアカウントにも共通するのは、「中の人」が顔を出さずとも“ちゃんと伝わっている”ということ。投稿からにじみ出る“人らしさ”や“ブランドらしさ”が、自然とファンを生んでいます。
華やかなバズ投稿や尖った言葉づかいに目を奪われがちですが、実はその裏には地道で丁寧な“設計”があります。そんな姿勢を学ぶことができる、8つの企業アカウントを順番に見ていきましょう。
ちょっとニッチだけど学びの多いX企業アカウント8選
- 永江印祥堂(職人技×人情味)
- やすもと醤油(老舗×ゆるさ)
- 山芳製菓(地道な毎日投稿×丁寧な対話)
- 木村鋳造所(ものづくり×ユーモア)
- パイン株式会社(キャラ投稿×丁寧な返信)
- アイラップ(生活に密着した使い方提案)
- セメダイン(専門性×共感コミュニケーション)
- ツバメノート株式会社(伝統×丁寧な情報発信)
■ 永江印祥堂
- アカウント:@nagaeinsyoudou
- フォロワー数:6.7万人
島根県の小さなハンコ屋さん「永江印祥堂」。
SNSを始めたきっかけは、リアル店舗の売上減をオンラインで補うため。
でもその投稿内容は、単なる商品紹介にとどまりません。1円玉サイズの印鑑に円周率160桁を彫るなど、思わず驚く“職人技”を紹介する投稿が話題となり、瞬く間に人気に。フォロワー数は6万人を超え、今や全国から注文が来るように。
中の人は、社内の和やかなやりとりや雑談も投稿しており、「人」に惹かれてフォローするファンも多数。ついかしこまってしまったり堅くなりがちな企業SNS運用の中で、“正直すぎる”姿勢が親近感を生んでいるようです。
地方・小規模事業者の参考になる運用例です。
■ やすもと醤油
- アカウント:@yasumotoshoyu
- フォロワー数:9.1万人
創業は1885年。島根県で長く愛されてきた老舗の醤油メーカーが、いまXで大人気です。
「フォロワー40人で褒められた!」というバズ投稿をきっかけに注目を集め、現在のフォロワー数は9万人超。
投稿内容は、社長夫妻とのほっこりエピソード、現場の一コマ、日々のあいさつなど、すべてが親しみやすく“人の温度”を感じさせるものばかり。まるで近所の人と話しているような雰囲気です。
コメント欄への返信も非常に丁寧で、企業公式とは思えない距離感に驚かされます。
商品を押しつけるのではなく、「気になるから調べてみたくなる」「応援したくなる」という流れを自然に作る──そんな“応援されるアカウント”を体現しています。
■ 山芳製菓
- アカウント:@yamayoshiseika
- フォロワー数:23.4万人
「わさビーフ」でおなじみの山芳製菓。
公式アカウントでは、毎日「〇〇の日」にちなんだ投稿を欠かさず行っており、企業発信としての地道さと丁寧さが際立ちます。
たとえば「〇〇の日」に合わせたイラスト投稿や、マスコットのぬいぐるみを使ったゆるい投稿など、キャラクター性のある投稿が人気。さらに、ほぼすべてのリプライにリプ返しをしている点も見逃せません。
「お菓子のアカウント」で終わらせず、ユーザーと会話し、交流し、寄り添うことで、企業の印象もグッと身近なものに。ファンづくりの“王道”をしっかり積み重ねる、まさに好事例です。
■ 木村鋳造所
- アカウント:@KimuraFoundry
- フォロワー数:6万人
1927年創業の鋳物メーカー・木村鋳造所。
投稿内容は、技術解説……ではなく、ナマコの忘れ物連絡、アイス補充の様子、社員の日常などなど、とにかく自由!フォロワーとの距離を近づけるような投稿が次々とバズり、BtoBにも関わらず6万人以上のフォロワーを獲得しています。
でも、単なる“おもしろ投稿”で終わらないのがこのアカウントの魅力。製品づくりのこだわりや現場の様子をしっかり伝える投稿もあり、遊び心と誠実さのバランスが絶妙です。
「何をやってる会社かはよく知らないけど、応援したくなる」。そんなふうに思ってもらえる企業アカウントが、ブランドを未来へつなぐのかもしれません。
■ パイン株式会社
- アカウント:@pain_ame
- フォロワー数:21万人
「おパよ〜」「〜しま( ´◎`)スー」など、独特の語尾や言い回しがクセになる、パインアメ公式アカウント。
中の人・マッキーさんが一人で運用しており、毎朝のあいさつ投稿や“ゆるい時報”が定番コンテンツになっています。
投稿スタイルは極めてフレンドリーで、フォロワーからのリプライにも細やかに対応。企業というより“キャラクター”に近い存在として、ファンとのあいだに特別な関係性を築いています。
もちろん、商品紹介やキャンペーンのお知らせも忘れませんが、それも「いっしょに楽しむ」テンションで届けられるのがパインアメらしさ。長く愛される理由が、投稿の端々から伝わってきます。
■ アイラップ
- アカウント:@i_wrap_official
- フォロワー数:33.9万人
日常生活から防災まで幅広く活躍する“袋のラップ”ことアイラップ。
その公式アカウントは、実用性と親しみやすさを兼ね備えたアカウントとして知られています。
画像付きの丁寧な使い方紹介や、災害時の活用方法など、暮らしに役立つ投稿が中心。一方で中の人自身のコメントも多く、どこか“手書きの説明書”を読むような温かさがあります。
また、ユーザーの投稿(UGC)を積極的に引用し、日常の中でのリアルな使用シーンをシェア。
アイラップという製品に“ストーリー”を加える工夫が、ブランドの魅力を自然と高めています。
■ セメダイン
- アカウント:@cemedinecoltd
- フォロワー数:8.8万人
「おはダイン!」のあいさつでおなじみ、接着剤メーカー・セメダインの公式アカウントは、硬派な製品をユーモアと愛で包んで発信しています。
商品を売ることではなく、“ファンを作ること”を目的にしているため、投稿内容は接着剤にまつわる日常の豆知識や雑談が中心。コメントへの返信も非常に丁寧で、時にはDIYの相談にものってくれるなど、専門性と人間味を両立させた運用が光ります。
また、他社アカウントとの絡みも積極的で、SNSならではの“横のつながり”も構築。
企業の顔でありながらも、親しみと信頼を感じさせる好例です。
■ ツバメノート株式会社
- アカウント:@TSUBAME__NOTE
- フォロワー数:3.7万人
クラシカルな黒表紙で知られるツバメノート。
見た目はまさに“昔ながら”ですが、公式XアカウントではSNSらしい柔らかなトーンで、こだわりや舞台裏を発信しています。「今年もデザイン変更しません!」という恒例投稿や、ノートの構造を紹介する“解体図”など、老舗ならではの誠実な製品づくりが伝わるコンテンツが特徴。
頻繁な投稿ではなく「1週間に5回のどうでもいいツイートより、1回の気持ちのこもったツイート」を意識しているという中の人の姿勢も印象的です。
少ない投稿でも確実にファンをつかむ、“リソースが限られていてもできる運用”のヒントが詰まったアカウントです。
共通して見えてきた、ファンを生む企業アカウントの「中の人」設計
ここまで紹介してきた8つのアカウントは、「なぜファンが生まれているのか?」という視点で見るととても示唆に富んでいます。
それぞれまったく違う業種・会社規模ですが、実は“伝え方”に共通しているポイントがいくつもあるのです。
✔️ 1.「商品」だけでなく「人」に惹かれる構造をつくる
多くのアカウントでは、製品やサービスの紹介に加えて、“日常”や“雑談”、会社の雰囲気などを発信しています。
とくに小規模企業やBtoB企業の場合、「なにを売っている会社か知らないけど、なんか好き」な状態を目指すことがとても有効です。まず“人”に惹かれてもらうことで、結果的に商品やサービスへの関心にもつながります。
✔️ 2. ユーザーと“会話”をする意識を持つ
どのアカウントも共通しているのは、リプライへの返信やUGCへの反応がとても丁寧なこと。
一方通行の「お知らせ」ではなく、「見てくれてありがとう」「一緒に楽しもう」という双方向のコミュニケーションを大切にしています。これは中の人が個人でなくとも、企業の温度感として伝わる部分です。
✔️ 3. 無理に“ウケ”を狙わず、自分たちの言葉で続ける
バズらせよう、ウケようとする投稿ではなく、企業や中の人の“素直な言葉”が多いことも印象的でした。
テンプレに頼らず、自分たちの言葉で、自分たちのペースで、でもしっかり継続する──これが何よりも難しく、そして信頼を育てる道でもあります。
“好き”を育てる、これからの企業アカウント運用へ
SNS運用において正解はひとつではありませんが、「ちょっとニッチだけれど強く愛されている」アカウントたちは、等身大の企業の魅力を伝えるモデルとして非常に参考になります。
あなたの会社らしい言葉で、あなたの会社のファンを、今日からゆっくり育てていきましょう。